
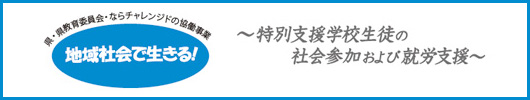
活動日誌 2011年 5月
2011年(平成23年)5月15日
~「奈良県新しい公共のモデル事業」公開プレゼンテーション ~
「地域社会で生きる!特別支援学校生徒の社会参加および就労支援」
〈協働提案〉:奈良県・奈良県教育委員会・NPO法人ならチャレンジド
●主催者:奈良県協働推進課 ・奈良市保健所・教育総合センター


行政・NPO等の協働活動により、「地域の課題」を解決していく平成23・24年度事業の公開プレゼンテーションが行われた。当グループは、県障害福祉課主幹・県教育委員会学校教育課主幹・ならチャレンジド理事長がプレゼンテーションに臨み、熱意をもって当事業の先進性・必然性を訴えた。
応募数は14事業。採択数は6事業。採択の発表は5月25日頃になる見通し。
【プレゼンテーション】
1. 奈良県・奈良県教育委員会・NPO法人ならチャレンジドは、心をこめて提案いたします。
本事業は、特別支援学校生徒の職場実習・社会参加の機会を新たに創りだすものです。
2.これまで、総論賛成・各論反対の見本のように、職場実習は「前例がない!」の一言で、
断られてきました。
昨年、NPO法人ならチャレンジドは、保護者と共に熱意をもってアプローチし、
南都銀行・奈良県農協・奈良交通・春日大社・薬師寺・大神神社様等は
初めて実習生を受け入れてくださいました。
今回の事業へも参加表明されています。ありがたいことです。
3. この度、16もの県内代表的な事業所・団体がひとつになり、
全国初の協働がスタートできることをとてもうれしく思います。
県・県教育委員会・NPOがなしえた官民協働の公的システムです。
〈システム化〉は現実を変える大きな力です。
職場実習・社会参加において、生徒は驚くほど、大きく成長します。
同時に、生徒と関わるすべての方々も変わっていきます。
「人が変わる」すなわち「地域が変わる」ことです。
障害ある生徒だけではなく、行政・企業・地域、すべての方々が幸せになっていくのです。
4. 地域社会で生きる!とは、暮らしを基盤にすることです。
就労を重要な切り口として、学校と企業の協働関係を打ち立てます。
同時に、市町村をプラットホームに、学校と地域社会がつながる取り組みです。
7月の「差別をなくす市民集会」は、絶好の機会であり、生徒たちが受付で参加します。
5.このモデル事業は3つの方向をもっています。
① 県の成功モデルをもって、地域に根づいた市町村単位の協働の構築をめざします。
② 特別支援学校生徒からすべての障害者へ対象を広げます。
③ 「金の切れ目が事業の終わり」とならないためにも、
人が育ち、熱い思いを持つ人が自立した関係でつながることをめざします。
審査員のみなさん! 私は、3日前、奈良東養護学校PTA総会において講演をいたしました。保護者は、長年の夢・思いを込めて本事業へ絶大な期待を寄せています。 障害ある生徒が誇りをもって社会のステージで活躍できること、その実現こそが私たち提案者の唯一の願いです。 本事業が採択されますよう心からお願いいたします。 ありがとうございます。

【様式11】
別紙
支援を申請するモデル事業
新しい公共の場づくりのためのモデル事業分)
モデル事業名 |
~地域社会で生きる!~ |
事業実施 |
奈良県 |
事業概要 |
行政(県・県教育委員会)・学校・事業所・PTA(保護者)・NPOが新たな官民一体となった協働関係を構築し、ダイナミックに障害者の社会参加と就労への道を切り拓く取り組みである。 特徴は、就労への入口である〈職場実習〉と〈社会参加〉を新たに創出することにある。 1.就労支援(実習先の開拓および実施、学校での就労講習等) 2.社会参加 |
事業内容 |
*県内全域を対象として、下記の事業を行う。 1.就労支援 ・これまで、学校・PTAが公共施設・民間事業所へ職場実習お願いするも、「前例がない!」と断られ続けてきた。就労支援を掲げる民間組織さえも大きな成果が出せなかった領域である。 ・昨年、NPO法人ならチャレンジドは保護者と共に果敢にアプローチし、6町の公共施設と県内代表的事業所(企業・神社・寺)が初めて職場実習を受け入れた。今回、その事業所も私たちと協働して取り組む。 ・県は、昨年度、障害福祉課に障害者雇用推進係を設置し、障害者の雇用推進を県政の重要な施策として積極的に取組を進めている。 本年度、部局を越えた人的配置を行い、特別支援学校の進路指導に精通した人材を県障害福祉課に配置し、県行政と県教育委員会が、一体となった取組を進めている。 ・特別支援学校生徒(障害者)の社会参加と就労を飛躍的に拡大する 絶好のチャンスである。 (1)職場実習先(市町村・企業)を新規に開拓 (2)職場実習の実施 (3)特別支援学校での就労講習 2.社会参加 ・住民と密接な市町村において、社会参加の仕組みづくりから始める。 ・今回、県・大淀町との協働をモデルケースに、この2カ年ですべての市町村で構築をめざす。 (1)市町村主催イベントの社会参加 (2)県等イベントの社会参加 ・地域交流コンサート ・地域交流ふれあい集会 3.広報 ・行政・学校・保護者・企業・県民等へ (1)県、県教育委員会による広報 (2)広報誌の発行 (3)NPOホームページへの掲載 (4)市町村広報誌への掲載依頼 (5)報道機関への情報提供 4.保護者ボランティア等の育成 ・準当事者である保護者が自ら主体的に関わり、その思いが反映する運 営を行う。そのことがNPOの人的充実へとつながる。 (1)保護者スタッフが、事業所の新規開拓をする。 (2)PTAと連携し、保護者の本事業ボランティア参加を促進する。 (3) 企業経営・障害者就労経験あるスタッフが、本事業に従事する。 5.会議体の運営 ・年2回、全体会を開催する。 |
マルチステークホルダー |
・奈良県・奈良県教育委員会 ・NPO法人ならチャレンジド 2011年6月 事業開始のキックオフ全体会議 |
支援額/ |
10,000千円 / 10,000千円 |
事業期間 |
2011年6月~2013年3月 |